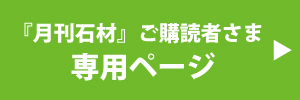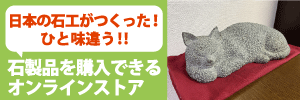一般研究員によるトピックス!!
石文化研究所に登録されている一般研究員による情報ページです。
【祈りの石巡り】彼は光源氏のモデルだったのか?清凉寺宝篋印塔・源融塔(京都市)
1月下旬のこと。京都清凉寺の源融(みなもとのとおる)のお墓を見てきました。

源融は源氏物語ファンの間では光源氏のモデルになった人物として知られており、百人一首には「河原左大臣」の名で以下の句が選出されています。
陸奥(みちのく)の しのぶもぢずり 誰(たれ)ゆゑに
乱れそめにし われならなくに
※陸奥が彼にとって重要な地だったことは後述します。
清凉寺は元々、源融が持っていた嵯峨の別邸があった場所とされており、源氏物語の中で源融没後、光源氏の手によって「嵯峨の御堂」として改修造営したとされる寺院と伝わります。
実在した源融と、古典の主人公を由来を持つという、史実とフィクションが織り交ざった伝説が伝わる、京都ならではの古刹。
それでは源融という人物、なぜ源氏物語に影響を及ぼし、後世へどう伝わり、そしてお墓が建てられたのでしょう。

彼の生前の姿を探しに、まずは鴨川の畔(下京区木屋町通五条下ル)に立つ源融の邸宅跡の碑へ。
「源融河原院址」と刻まれています。
源融(822年~895年)は平安時代初期、嵯峨天皇の息子として生まれますが、源姓を与えられ臣下として仁明天皇→文徳天皇→清和天皇→陽成天皇→光孝天皇→宇多天皇と仕え続けました。
しかもこの方、74歳で人生を全うしており、平均寿命が20~30代と言われた平安時代では驚異的な長寿。それだけでもインパクトがありそうな人物です。
“ザ★政界のフィクサー”感が漂います。
彼について調べていくと、興味深いエピソードが京都市内に伝わっています。

源融は、この鴨川の畔に4町(8町という説も)もの広さを持つ大邸宅「河原院」を所有していたと伝わります。
4町というと1町=120m四方が四つ並んだ、境界の大通りを合わせると一辺が250mにもなる広大な敷地です。もはや一つの町と言っても良いでしょう。
彼は、その邸宅内に、東北に任官した時に見た塩竃の風景を再現しようとします。
水を引き込み海に見立てた池を作るだけでは足らず、大阪湾から海水を毎日運び込ませ、海藻に海水をかけ、焼いて塩を取り出す当時の製塩風景をも再現させていたそうです。
塩が目的というより、源融は海辺の暮らしの風景を懐かしむためと思われます。邸宅内は毎日がお祭り騒ぎだったのではないでしょうか。
自分たちは日本神話の中の海彦山彦たち神々の子孫であるという、平安貴族のプライドが垣間見える一面です。

河原院と言えば「幽霊」を想像する人も多いようです。
源融の死後、彼の子孫たちは広大な河原院を維持することができず宇多天皇に譲られますが、手を入れられることなく荒廃します。
廃墟に何者かいるのでは、と人の心が揺さぶられてしまうのは昔から変わらないようで、926年6月25日、源融の亡霊が現れたという古記録があります。
退位後の宇多法皇が妻の京極御息所と一緒にいたところ、妻が源融の霊によって頓死(その後加持によって蘇生)したという記録もあります。
こうして、ザ★政界のフィクサー源融の栄華伝説と共に、河原院は有名な廃墟&心霊スポットとして都の人のうわさに頻繁にのぼっていたのでしょう。
紫式部もそのような噂を聞き、源融の死後から約100年後、源氏物語の中に河原院を思わせる廃院と幽霊を登場させます。
光源氏と逢瀬中の夕顔が頓死する有名な場面です。
こうして源融は源氏物語の中で重要場面(特に邸宅の描写において)で登場しています。
彼の皇統でありながら臣下という立場や、栄華を極めた点で光源氏と確かに重なる面はあります。
ただ、当時、源融と同じような境遇の人物も多くいて、光源氏の寿命と全く異なることを考えると、紫式部が源融を光源氏のモデルにして描いたと言いきることは難しいのかもしれません。

源融が光源氏のモデルとされた説の一番の有力根拠は、源融の河原院と光源氏が住んだ六条院が同じ広さ、間取りだったと、室町時代の解説本『河海抄』に書かれたことによります。
一方で興味深いのは、源氏物語の中で六条院と河原院を明確に区別した記述があり、紫式部は皇族にふさわしい「源融存命中の河原院」を光源氏の邸宅イメージに取り入れたという言い方が自然かもしれません。
河原院の跡地の碑の背後には祠が入った建物がありました。
その裏には鴨川がありますが当時は同じ位置を流れてはいなかったでしょう。
約1100年以上もの昔の源融の栄華を感じさせるものをここで見つけることは難しかったです。
しかし、源融は嵯峨野、宇治に別邸を持っており、それぞれ清凉寺、平等院と姿を変え、その広大な敷地に現代の庶民は驚かされるばかりです。

 源融の嵯峨野の別邸は、今は清凉寺。
源融の嵯峨野の別邸は、今は清凉寺。
堂々とした仁王門と本堂(釈迦堂)。清涼寺には平安時代からの遺構は残っておらず、こちらは江戸時代に再建されたものです。

源融の墓は鎌倉時代後期に建てられた宝篋印塔です。
花崗岩製で高さは約1.6m。
このお墓が建てられたのは源融の没後約400年のこと。時代が貴族から武士の世の中に変わってもなお、京都の人々の話題に上っていた大物人物だったことが伺えます。

笠の段型は、下が三段で、上には六段刻まれています。階段を正確に刻む石の加工は技術が発達した今でも大変な箇所です。当時の石工の情熱を感じさせます。

視認が難しいのですが、八面の隅飾り(笠の四隅に置かれた尖塔)には梵字「アー」が彫られ、塔身には梵字で金剛界四仏(東:宝生如来・西:不空成就 ・南:阿弥陀如来・北:阿閦如来)が彫られているそうです。
お墓というと没後すぐ建てられるイメージがありますが、源融のように死後4世紀以上も経つと、生前の彼の姿を知る人は当然皆無。
子孫もバラバラになっていることでしょうから、今の人が思う建墓のタイミングをはるかに超越しています。
鎌倉時代に起こった「石造物建立一大ムーブメント」についてはまたの機会に取り上げたいと思いますが、石に関わる者としてはとりあえず、当時の技術で複雑な宝篋印塔を加工するのは本当に大変だったはずです。
当時仕事を依頼した人にも、相当の情熱・財力・人脈がないと石工は引き受けてくれなかったのではと、勝手に憶測・妄想してしまいます。
400年前の有名人のお墓を建てようと思い立った鎌倉時代の人々の思いに色々と思いを巡らせる、これも石造美術鑑賞の面白さの一面ですね。
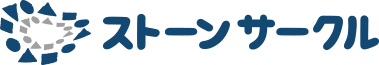


 前の記事
前の記事