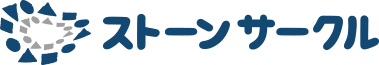特別企画
お墓や石について、さまざまな声をお届けします。
人は死んだらどこへ行けばいいのか―東北大学大学院文学研究科 教授 佐藤弘夫
●著者インタビュー/『月刊石材』2021年7月号掲載
人は死んだらどこへ行けばいいのか
東北大学大学院文学研究科 教授 佐藤弘夫
 佐藤弘夫先生
佐藤弘夫先生
東北大学大学院文学研究科の教授である佐藤弘夫先生が著した『人は死んだらどこへ行けばいいのか 現代の彼岸を歩く』(興山舎)が2021年5月1日に発刊された。本書は『月刊住職』(興山舎)の好評連載「日本人はいかに弔われてきたか」の2018年9月号から2020年6月号までの22本を編集したものである。
原始から古代、中世、近世、近代、現代における「弔いのカタチ」を見ていくと、死者との共存の物語がいかに変化し、また仏教が葬送供養において、人々の想いを受け止めてきたかがわかるという。
佐藤弘夫先生に、「霊魂」や「カミ」、「先祖」などについて話を伺った。
宮城県松島湾に浮かぶ、かつて霊場であった雄島。長さ200mほどの小島で、多数の板碑が残されている
モノに霊魂があると意識するのは、室町時代以降
――いろいろな弔いの場所を見て回られていると思いますが、印象的な場所はありますか?
佐藤弘夫先生(以下、佐藤) インパクトのある場所は結構あります。心に残る場所は、自然だけではなく、そこに暮らす人々の思いが長い間、染み込んだような、蓄積された場所ですね。
今回の本(『人は死んだらどこへ行けばいいのか現代の彼岸を歩く』興山舎)で紹介している場所は、そのような場所です。そこを歩くと、向こうから語り掛けてきます。ちょっと気障ないい方かな(笑)。ただ、一回だけではダメで、何度も行って、その場所と関係性ができてくると、向こうから語り掛けてきて、こちらも見えなかったものが見えてくる。だから、できるだけ何度も行くようにしています。
 佐藤弘夫著『人は死んだらどこへ行けばいいのか 現代の彼岸を歩く』(興山舎)
佐藤弘夫著『人は死んだらどこへ行けばいいのか 現代の彼岸を歩く』(興山舎)
――いずれも興味深い場所でした。コロナが収束したら、ぜひ足を運びたいと思います。さて、本題に入りたいと思いますが、日本列島において、「たま」(霊魂)を意識したのは、いつ頃なのでしょうか?
佐藤 いまの常識的なイメージだと、日本人というのは、あらゆるモノに霊魂の存在を認めて、それを聖なるものとして崇めるという伝統があるとよくいわれます。またそれは「縄文時代からの伝統」とされていますが、私はそうではないと思っています。縄文時代の人たちが、一つひとつのモノに霊魂を見出して崇めていたかというと、そのような事実はないと思っています。
『日本書紀』のなかに、「草木がことごとくものをいう」という言葉がありますが、草木に霊魂があって、その霊魂が語り掛けてくるということではなく、人間と自然が同じレベルで、ごく自然に付き合うような状況だったと思います。ですから、いろいろなモノに霊魂があると意識するのは、室町時代以降だと思っています。
――縄文時代の墓地は、どう考えればよいのでしょうか?
佐藤 当時は、遺体と亡くなった人の人格は一体化していたと思います。たとえば、犬は仲間の犬が死んだ場合、そこに霊魂があるとは思っていないと思います。ただ、最初は悲しがって死んだ犬を舐めるなどしています。人類も同じで、それが最初の感覚なのではないかと思っています。
縄文人は墓地をつくって遺体を大切にしますが、それは霊があるからということではなく、動かなくなった仲間の埋葬です。そして縄文時代のある時期から、目に見えないモノに対するイメージが膨らんでいったのではないかと思っています。
 縄文時代の墓地だったとされる大湯環状列石(野中堂環状列石) 出典:JOMON ARCHIVES(縄文遺跡群世界遺産保存活用協議会撮影)
縄文時代の墓地だったとされる大湯環状列石(野中堂環状列石) 出典:JOMON ARCHIVES(縄文遺跡群世界遺産保存活用協議会撮影)
人類が初めて人間を超えるカミを感知したのは、人知の及ばない自然現象に対してだったと思っています。それは、やがて土偶などの像として具体的なカタチを与えられて、人々に共有されるようになります。
しかし弥生時代になってくると、カミは抽象化され、目に見えないカミを呼んで来て祀るという儀式が起こってきます。そのあたりになってくると、目に見えないモノに対するイメージがだいぶ膨らんでくる。ただそれはあくまでもカミであり、特別な存在であって、万物が目に見えないモノを持っているという感覚には、なかなかならなかったのではないか。
普通の人たちが死後、ご先祖様になっていくのは江戸時代以降
――ご先祖様がカミと認識されるのは、いつ頃からでしょうか?
佐藤 いろいろなところに書いていますが、私はごく普通の人たちが死後、聖なる存在、カミ、ご先祖様になっていくのは、江戸時代以降だと思っています。
お墓は、縄文時代から弥生時代のある時期まで、大きさなどに違いはありません。ただ、考古学者の指摘ですが、弥生時代のある時期から、権力者のお墓が特別な存在になって、巨大化して山の高い所につくられるようになり、平地から登り始めます。
では、「なぜ山なのか」という問題ですが、山が当時、どのようなイメージだったのかというと、「亡くなった人が行く」といったことを書いた古い文献はありません。山はカミが居る場所であり、人間は安易に入ってはいけない場所でした。
では、「なぜカミが山に居るのか」というと、「日常生活の汚れから離れたきれいな場所だから」という議論があります。ですから、権力者のお墓が山に登るということは、「権力者が特定の人であり、普通の人ではない」と解釈する動きが起こってくるからではないかと思っています。
そうして権力者をカミにしていく。それが意図的になされているのが前方後円墳で、私の考えでは古墳は人工的な山であり、カミをつくるための装置だと思っています。そういうなかで、ある特定の人がカミになっていく現象が起こってくるのだと思っています。誰も受け入れてくれませんが(笑)。
内館牧子さんが2021年3月に『小さな神たちの祭り』(潮出版社)という本(小説)を出しました。この本は津波被災地を舞台にして、亡くなった人が別の世界で同じように生活をしていて、そこを行ったり来たりする話です。題名にある「小さな神たち」とは亡くなった人のことです。
 内館牧子著『小さな神たちの祭り』(潮出版社)
内館牧子著『小さな神たちの祭り』(潮出版社)
内館さんとは親しくさせていただいており、本をいただいたときに、「本のネーミングが素晴らしい」といったら、とても喜んでくれました(笑)。いずれにしても、亡くなったごく身近な人をカミとするというのは、おそらく江戸時代からだと思っています。