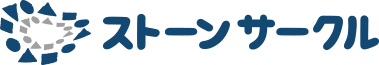特別企画
お墓や石について、さまざまな声をお届けします。
人は死んだらどこへ行けばいいのか―東北大学大学院文学研究科 教授 佐藤弘夫
――磐座はカミの依り代とされていますが、どんなカミの依り代なのでしょうか?
佐藤 見えない存在のイメージが膨み、特別な存在のカミが意識され、その居場所が清浄な山であり、その依り代として磐座があるという構図ではないかと思います。『日本書紀』や『古事記』ではカミに人格があり、人の姿になっていますね。
――なぜ、石なのでしょうか?
佐藤 不思議ですね(笑)。人間の本能が石を選ぶのではないでしょうか? 立派なモニュメントは世界中どこへ行っても石を使っていますし、一番壊れないモノのシンボルなのでしょう。
私は山歩きが好きなのですが、山を歩いていると立派な岩がたくさんあります。やはり、インパクトがありますよね。
中世は、この世とあの世をつなぐものが必要だった
――仏教は、なぜ中世に栄えたのでしょうか?
佐藤 石の話からすると、中世になると石塔がたくさんつくられます。東日本だと板碑が万単位でつくられ、歩けばどこにでもあるような感じですが、板碑はこの世とあの世を結ぶような存在です。江戸時代になってくると、死者の依り代のような感じですが、おそらく中世では、死者の霊魂が板碑にいるという感覚はなかったと思っています。
中世は目に見えない世界のイメージが、すごく膨らむ時代です。その理由は人が多く亡くなるからであり、自分がいつ死ぬかわからない状態にあるからです。それは世界中一緒で、そのような状況になると、目に見えない世界のイメージが膨らみます。
人は、命がこの世だけで終わるのには耐えられず、生と死の世界があって、仮にここで死んだとしても、もう一つの世界があると考える。そうすると、この世とあの世をつなぐものが必要になり、たとえば、それは仏像ですよね。仏像を拝む理由は、その仏像の力であの世に送り出してもらう、ということだと思います。
だから、そういうつなぐモノとして石があり、板碑が非常に大きな役割を果たす。石は聖なる存在なのだと思います。板碑は非常にシンプルで、梵字を彫ってあるだけですが、そこに骨を納めて皆が祈りを捧げています。そうすることによって、聖なる扉が開いて、この世からあの世に行くことができる、というイメージを私は持っています。
 雄島(宮城・松島湾)にある最古の板碑。梵字「バン」と、弘安八年酉乙八月彼岸中日(1285年8月15日)の銘が残っている
雄島(宮城・松島湾)にある最古の板碑。梵字「バン」と、弘安八年酉乙八月彼岸中日(1285年8月15日)の銘が残っている
――それらのつなぐモノには、死者供養という意味もありますか?
佐藤 もちろん、そうですね。
死者は江戸時代も多かったのですが、ただ江戸時代になってくると、庶民がだんだんと一ヵ所に定住するようになります。中世は流動的な時代でしたが、江戸時代になると家ができて村ができ、「親から子へと受け継がれていく家がある」という感覚を、庶民層まで持つようになってくる。
中世は流動的であり、どこで死ぬかわかりませんので、死者供養は仏様に任せるしかなかったのだと思います。任せるためには、その仏様が大きな力を持った存在でなければならず、阿弥陀仏がその代表であり、絶対的な救済者というイメージがどんどん膨らんでいく。法然上人や親鸞聖人の思想が、その代表でしょう。
江戸時代になってくると、それが徐々に世俗化していくと同時に、生きている人が家のなかで死者を供養していくようになります。仏様にあまり任せなくても、死者をご先祖様として、子孫が長い時間を掛けて供養してくれる。むしろ、その方が望ましいわけです。
本のなかで書いていますが、山形県庄内地方にある三森山への登山は、普段はタブー視されていますが、年に2日間(8月22日、23日)だけ山に登ることができ、そこで先祖と語り合うことができるといいます(モリ供養)。
山に登った人が山から下の風景を見ると死者の目線になります。だから、「自分が死んだときにはこの山にいて、子孫が会いに来てくれるのは嬉しい」といった安心感が、地域の人々を支えていたと思います。そのサイクルが機能していた。ただ、それがいま機能しなくなってきています。その結果、人々の意識が死を恐怖の世界としか見ない風潮と結びついてきているように思います。
山形県庄内地方にある三森山(左)と、山から望む庄内の田園風景(中)。毎年8月22日、23日だけ、「モリ供養(先祖供養)」として山に登ることができる。「モリ供養」の核心である大施食供養の施餓鬼棚(右)。写真提供:佐藤先生
江戸時代は、生と死を貫く安定したストーリーが共有されていた
――江戸時代に墓参が増えたのは、生活が安定したからでしょうか?
佐藤 そうですね。あとは生と死を貫く安定したストーリーが共有されていた。いつかは死ぬけれども、死んだらこのお墓に入り、子孫と折々に語り合って、いずれまた、この地に蘇ってくるといったようなストーリーです。
私の孫は、95歳になる祖母と顔がそっくりなんです(笑)。昔は95歳まで生きるようなことがなかったでしょうから、孫がおじいちゃんやおばあちゃんの生まれ替わりと思ったというのは、そのとおりだと思います。親族はたくさんいるのですが、その孫だけそっくりなんです(笑)。
――良源上人(912-985年)が「石の卒塔婆を建てて、お参りを」といった遺言(ご遺告)を残していますが、これはどう考えればよいのでしょうか?
佐藤 良源上人のクラスになると、自分は救済者という感覚があったのだと思います。要するに、この世とあの世をつなぐ存在であり、仏像と同じです。板碑に祈りを捧げると、「あの世に行ける力をもらえる」ということと同じです。
 比叡山・横川にある天台宗中興の祖といわれる良源上人の御廟
比叡山・横川にある天台宗中興の祖といわれる良源上人の御廟
中世は聖人信仰が盛んです。その聖人はなぜ信仰されたかというと、人々をあの世に送り届ける力があったからです。聖徳太子はその代表で、中世の聖徳太子信仰はものすごく盛んでした。
先日、聖徳太子とコロナウイルスについて文章を書きました。聖徳太子とコロナウイルスは同じような運命を辿る、という内容です(笑)。
聖徳太子はある時期まで聖人で、この世とあの世をつなぐ役割を果たしていました。ウイルスは昔、疫病神と呼ばれていましたが、カミなんですよね。だから、叩き潰してはいけないんです。あくまでも、尊重して褒めたたえて煽てあげて帰っていただく。
ところが、近代になると聖徳太子は人間になり、一万円札にも登場するようになってしまう(笑)。コロナウイルスも、いまはカミではなく、叩き潰すような存在になっています。昔は疫病神のメッセージを聞こうとしていました。人々に害をもたらすけれども、そこには何かしらメッセージが込められているはずだと考えていました。
だから、私はコロナウイルスのメッセージに耳を傾ける必要があると思っています。いまの議論は、すべて人間の目線なんですね。逆にコロナウイルスの目線で見たら、何が見えるのか? そうした発想が大事だと思っています。