墓を訪ねて三千里
墓マイラーであるカジポン・マルコ・残月さんによる世界墓巡礼のレポートです。
夏目漱石 ~文豪は“安楽椅子”でくつろでいた
 漱石の墓は安楽椅子の形。
漱石の墓は安楽椅子の形。
雑司ヶ谷霊園でも一際目立つ、唯一無二の造型だ
大阪在住の僕が上京の際によく訪れる墓地は、都心で交通の便が良い雑司ヶ谷霊園、青山霊園、谷中霊園だ。中でも雑司ヶ谷は夏目漱石の他、小泉八雲、永井荷風、泉鏡花など文人が多く眠っており好んで墓参している。
漱石の本名は夏目金之助。1867年、幕末生まれ。高校の英語教師をしていた33歳の時に、国の命令で英国へ留学生として派遣される。ロンドンでは孤独感から神経衰弱が悪化し部屋に閉じこもった。やがて、文部省に「夏目金之助発狂す」と報が入り、留学は2年強で終了。
「この世に生れた以上、何かしなければならん。といって何をしてよいか少しも見当が付かない。私はちょうど霧の中に閉じ込められた孤独な人間のように立ちすくんでしまった」(漱石)。
帰国後、教壇に立ちながら悩む漱石に、友人の高浜虚子が「沈うつな思いをありのまま吐き出せば気晴らしになる」と小説の執筆を薦めた。
1905年、漱石は教師の日常を猫の目を通して書いた『吾輩は猫である』を発表し、好評を博す。
翌々年、人生の転機が訪れた。新聞社から専属作家の契約依頼がきたのだ。5人の子どもを抱えていた40歳の漱石は即答できなかった。既に東大に教授のポストが用意されていたからだ。名誉ある東大教授の職は、高収入で安定している。一方、作家は明日の保証すらない仕事。漱石は1ヵ月悩んだあげく、東大総長宛に辞職願いを提出した。この時の心境を彼は日記に残している。
「大学では4年間講義をした。食えなければ、いつまでも(職に)かじり付き、しがみ付き、死んでも離れないつもりであった。しかし近来の漱石は何か書かないと生きている気がしないのである」。
作家業に専念した漱石は、『三四郎』『それから』『門』と立て続けに名作を生み出したが、43歳の時に胃潰瘍が原因で修善寺温泉にて大吐血、生死の境をさ迷う。一命を取り留めた後、より精神世界に深く切り込んだ『行人』『こころ』を書き、最後の長編『明暗』のクライマックス直前に病没した。「胸に水をぶっかけてくれ!死ぬと困るんだ!」と死の床で訴えたという。
漱石に墓参する際は管理事務所で地図をもらおう。漱石の弟子・芥川龍之介が墓参にきて自力で辿り着けなかったほど霊園は広い。特徴的な墓石は、一周忌の折に「西洋の墓でも日本の墓でもない、安楽椅子にでもかけたといつた形の墓をこさへよう」(鏡子夫人)という話になり、建築士の妹婿が設計したという。
現在、漱石が晩年を過ごした漱石山房は漱石公園(新宿区早稲田南町)として整備されている。公園内の『猫塚』は夏目家のペット(犬、猫、小鳥)の合同供養塔だ。
人間のドロドロのエゴをあぶり出しつつ、根底はヒューマニズムを貫いた漱石。あの世があるならば、僕は他界後すぐに漱石先生に会いに行き『明暗』の結末を聞くつもりだ。
 漱石公園の猫塚は“吾輩”の猫の13回忌に建立。
漱石公園の猫塚は“吾輩”の猫の13回忌に建立。
戦災で倒壊し漱石37回目の命日に再建された
※『月刊石材』2012年11月号より転載

カジポン・マルコ・残月(ざんげつ)
1967年生。大阪出身。文芸研究家にして“墓マイラー”の名付け親。
歴史上の偉人に感謝の言葉を伝えるため、35年にわたって巡礼を敢行。2,520人に墓参し、訪問国は五大陸100ヵ国に及ぶ。
巡礼した全ての墓を掲載したHP『文芸ジャンキー・パラダイス』(http://kajipon.com) は累計7,000万件のアクセス数。
企画スポンサー:大阪石材工業株式会社
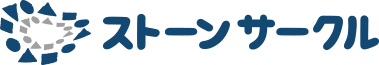


 前の記事
前の記事










