墓を訪ねて三千里
墓マイラーであるカジポン・マルコ・残月さんによる世界墓巡礼のレポートです。
“俳聖”松尾芭蕉~自然や人生の洞察を深く歌い込み俳句を文学に昇華
 生涯に詠んだ句は約900句。義仲寺はJR膳所(ぜぜ)の徒歩圏内。
生涯に詠んだ句は約900句。義仲寺はJR膳所(ぜぜ)の徒歩圏内。
境内には義仲を愛した最強女性武将・巴御前の墓も
『月刊石材』創刊400号の記念回ということもあり、墓マイラーの大先輩かつ日本を代表する文化人である俳人・松尾芭蕉を取り上げたい。
芭蕉は1644年に伊賀国(三重県)で生まれ、18歳のときに文芸肌の藤堂藩士に料理人として仕え、俳諧の手ほどきを受けた。28歳で初の撰集を伊賀天満宮に奉納し、伊賀俳壇で実力を認められた。その後、江戸へ出て修業を積み、33歳で俳諧師の免許皆伝=宗匠となった。
当時の俳壇はユーモアの機知や華やかさを競う句ばかりが持てはやされていたが、芭蕉は静寂の中の自然の美や、魂の救済などを詠み込むことを目指した。街中の喧騒を離れて隅田川岸に草庵を結び、庭にバショウを一株植えたところ、見事な葉がつき評判になったため、号を“芭蕉”とする。
40歳、郷里に眠る母の墓参りをするため、奈良、京都、名古屋、木曽などを半年間巡り、紀行文『野ざらし紀行』をまとめた。母の遺髪が白髪だったことに胸を打たれこう詠んだ。「手にとらば消(きえ)ん涙ぞ熱き秋の霜」(手に取れば秋の霜のように熱い涙で消えてしまいそうだ)。有名な「古池や蛙飛込む水の音」を詠んだのは42歳。
信州、神戸、高野山と旅に明け暮れ、風雅に興じる日々を重ねるも、旅がラクすぎることに疑問を持ち始める。訪問先では土地の弟子が待ち構え最大限のもてなしをしてくれた。
過去の偉大な詩人達は、こんなぬくぬくとした旅で詩心を育んだのではない。もっと自然と向き合い魂を晒す本当の旅をする必要があった。そして“ちぎれ雲が風に吹かれて漂う光景に惹かれて旅心を抑えきれず”“東北を旅したいという思いが心をかき乱し、何も手がつかない状態”となり、古典に詠まれた歌枕(名所)を訪れるため、弟子の曾良を供に江戸を発った。ときに1689年3月(45歳)。
福島、宮城、岩手、山形、北陸地方を巡って岐阜に至るという、行程約2,400キロ、7ヵ月間の大旅行となった。「道路に死なん、これ天の命なり」(たとえ旅路の途中で死んでも天命であり悔いはない)と覚悟を誓っての旅立ちだった。この旅から俳諧紀行文『おくのほそ道』が生まれるが、芭蕉は練りに練って3年がかりで原稿をまとめ、2年をかけて清書を行ない、完成に5年を費やした。脱稿から約半年後、大阪にて50歳で病没する。
芭蕉は百人一首に名を遺す歌人・藤原実方の墓を探して笠島(宮城県名取市)に向かった。かつて西行法師が実方の墓前で歌を詠んでおり、何としても行きたかったが、大雨で道がぬかるみ体力の限界に達し、墓参を断念。歌に想いがにじむ。「笠島はいづこ五月のぬかり道」(嗚呼、笠島は一体どこなのだ……五月雨の泥んこ道でどうにもならず無念だ)。
墓マイラーとしてこの悔しさがよく分かる。金沢では現地で30代の愛弟子の訃報を知り、墓前で悲嘆を詠んでいる。「塚も動けわが泣く声は秋の風」(墓よ動いてくれ、この寂しき秋風は私の泣く声だ)。
芭蕉の亡骸は遺言に従って、弟子たちが滋賀大津・義仲寺に眠る源平時代の武将・木曽義仲の側に埋葬した。源義経でも頼朝でもなく、悪役として伝わる義仲。不器用にしか生きられなかった義仲を慕うところに芭蕉の優しさを感じた。
 墓は全国に8ヵ所以上あり、こちらは東大阪市の吉田墓地。
墓は全国に8ヵ所以上あり、こちらは東大阪市の吉田墓地。
わが子も墓マイラーの道をまっしぐら(当時1歳11ヵ月)
※『月刊石材』2014年1月号より転載

カジポン・マルコ・残月(ざんげつ)
1967年生。大阪出身。文芸研究家にして“墓マイラー”の名付け親。
歴史上の偉人に感謝の言葉を伝えるため、35年にわたって巡礼を敢行。2,520人に墓参し、訪問国は五大陸100ヵ国に及ぶ。
巡礼した全ての墓を掲載したHP『文芸ジャンキー・パラダイス』(http://kajipon.com) は累計7,000万件のアクセス数。
企画スポンサー:大阪石材工業株式会社
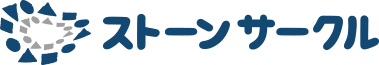


 前の記事
前の記事










