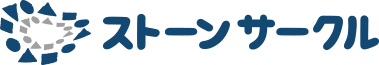特別企画
お墓や石について、さまざまな声をお届けします。
見事に蘇った常磐橋! ― ㈱文化財保存計画協会特任主任研究員 西村祐人さんに聞く
 解体修理が終わった常磐橋(橋長28.8m、橋幅12.6m)。中央橋台の水切石は、当初の姿に復元した。高欄の親柱・中柱等をライトアップする照明器具は、新たに設置したもの。左奥に見えるのが日本銀行(写真提供:㈱文化財保存計画協会)
解体修理が終わった常磐橋(橋長28.8m、橋幅12.6m)。中央橋台の水切石は、当初の姿に復元した。高欄の親柱・中柱等をライトアップする照明器具は、新たに設置したもの。左奥に見えるのが日本銀行(写真提供:㈱文化財保存計画協会)
東京駅日本橋口から徒歩数分の距離にある「常磐橋」(国史跡)の解体修理工事が2020年秋に完了した。
常磐橋は1877(明治10)年に高欄付き二連アーチ橋として竣工。関東大震災後の昭和期の修理を経て今日に至っていたが、2011年に発生した東日本大震災でアーチに損傷や変形が生じ、橋台の一部を残して2012年度から解体修理が行なわれていた(『月刊石材』2018年10月号・11月号で詳報)。
その被災状況の調査開始から工事完了まで丸9年。文明開化期に築造された、河川に架かる橋としては都内現存最古の石造アーチ橋が、平成と令和の時代をまたいで見事に蘇ったのだ。
そこで「常磐橋」修復プロジェクト第3弾として、「常磐橋解体修理工事」設計・監理を担当した㈱文化財保存計画協会・特任主任研究員の西村祐人さんをインタビュー。聞き手は西村さんの大学院時代からの恩師であり、常磐橋修理工事専門委員会(委員長=東京大学名誉教授・新谷洋二先生)の委員でもある東京大学工学系研究科社会基盤学専攻景観研究室・教授の中井祐先生に務めていただいた。
西村さんの「常磐橋」修復プロジェクトに込められた思い、また石材業界のあるべき姿を確認してほしい。
※『月刊石材』2021年1月号より転載
 西村さん(右)と中井先生。東京大学内の中井先生の研究室にて
西村さん(右)と中井先生。東京大学内の中井先生の研究室にて
(撮影時のみマスクを未着用)
■ 本当に元に戻せるだろうか?
中井祐先生(以下、中井) まずはお疲れさまでした。まだ終わっていないと思いますが、9年間ですよね。当初、この仕事に携わったのは、文計協(㈱文化財保存計画協会)のなかで「単に担当になったから」ということでしたよね。
西村祐人特任主任研究員(以下、西村) 当時、私は、城郭の石垣を修復するチームにいたのですが、社内で土木構造物を担当する人はわずかでしたし、他に適任者もいなかったのと、ちょうど宮崎県の日南市で堀川橋という石造アーチ橋の部分修理に携わっていたこともあって、私が担当することになりました。
2011年、東日本大震災が起きて、橋を管理する千代田区さんから「常磐橋が変形しているので見てほしい」ということで声が掛かり、被災状況の確認に行ったのが始まりです。
中井 近世末期から近代にかけて、主に九州で石橋がつくられていますが、保存や修復の技術やその事例なりが今日の土木技術界、また建設業界のなかで一般化され、共有されているという状況ではほとんどなかったと思います。
つまり、保存や修復経験の蓄積があまりないなかで、常磐橋の修復をしなければならない状況だったと思いますが、最初のころは何を考え、どんなことを思いましたか?
西村 修復事例の蓄積があるに越したことはありませんが、歴史的な建造物、特に土木構造物はいまの建造物とは違い、「その土地の材料や地形、風土のなかで、1回性のものとしてつくられてきた」ということでいえば、どんな現場でも、結局は一から考えなければならない部分が多くあります。まずは、数少ない修理事例から学びつつ、一つずつ課題をつぶしていくしかないと思っていました。
常磐橋はつくられてから140年ほど経っており、その間に石は馴染み、アーチも落ち着いています。解体はその積み重ねられた時間をいったん開放するということです。もちろん石は木のように縮んだり太ったりしない材料だとわかっていても、馴染んだものを一度バラバラにして、「本当に元に戻せるだろうか?」という点が一番心配でした。
中井 どんな事例を参考にしましたか?
西村 九州の石橋で、平戸にある幸橋、長崎や諫早の眼鏡橋、鹿児島の甲突川五石橋の一つである西田橋などです。
あらかじめ上げ越した支保工の上に石を組み上げ、最後に要石を入れ、支保工を下げたときに、アーチにしっかりと力が伝達され、きれいなかたちになるのか。そこが一番難しいところですが、これまでの事例を参考にしながらも、常磐橋固有の課題もあるので、そこは徹底的に検証を重ねて挑みました。
 アーチ下の支保工を下げるジャッキダウン時のようす
アーチ下の支保工を下げるジャッキダウン時のようす
(写真提供:文計協。詳細は『月刊石材』2018年10月号参照)
中井 常磐橋は達成しなければならない幾つかのクオリティ、またミッションがあったと思います。
一つ目は空積みのアーチ橋であり、構造物として安全なものを架けなければならないという点です。二つ目は、文化財としての歴史的な価値を継承しなければならず、つまり、文化財という価値軸のなかで修復をやらなければならないということです。そして三つ目は、歴史的な都市空間としてのクオリティを、しっかりと担保するということです。
大きく三つに分けることができると思いますが、西村さんのいまの話は一つ目のことになると思います。残りの二つはどうですか?
西村 二つ目の文化財の修復として、まず必要だったのは、常磐橋が日本の石橋文化のなかでどういう位置にあるのか、そして、修復の拠り所となる常磐橋の本質的な価値がどこにあるのか、というのを確認することで、そこに多くの時間を使いました。
常磐橋は文明開化の時代に、江戸時代の城門の石垣を取り壊した石材を転用し、突貫工事でつくられた橋です。解体すると、外観とは裏腹に、あり合わせの材料を使って、かなり無理をして組み上げたようすがわかりました。しかも空積みですし、その何とか成り立っているように見えるアーチは、現代の技術者の目には、とても不安なものに見えると思います。
しかし、それこそが文明開化という時代の世相の表れであると考えれば、継承すべきは、その不揃いな石で組まれた空積みのアーチということになるわけです。ですので、単純に均一な四角い石に取り替えてしまうことはできません。その不揃いな石はそのまま使いながら、再構築するということが重要で、そこに現代だからこその修復技術や新たなアイデアが求められました。
ともかく考えられる方法を、ひたすら試行錯誤しました。和紙の繊維を吹き付け、縁切りしながら石と石の間に超高強度モルタルを詰め込む方法は、この現場で開発されたオリジナルの修復技法です。修復保存は、実は、すごくクリエイティブなことだと思っています。
 和紙で縁切りしながら、栗石とともに超高強度モルタルを輪石の空隙に詰め込んだ(写真提供:文計協)
和紙で縁切りしながら、栗石とともに超高強度モルタルを輪石の空隙に詰め込んだ(写真提供:文計協)
三つ目の歴史的な都市空間についてですが、常磐橋は、東京駅から歩いて3分くらいのところにありながら、その存在を知らない人も多く、忘れ去られたように、ひっそりとある石橋でした。その周辺が将来、再開発され、大きく姿を変えていくことはわかっていましたので、単に震災で変形した橋を元通りに戻すということではなく、江戸城外郭正門であった、常盤橋という場所の成り立ちにもう一度フォーカスし、そこから修復を考えることで、後の都市再生の一つの核になり得るという自覚は、割と初期の段階から持っていました。都市空間のなかで、過去と現在をつなぎとめる接点としての役割を担うだろうという思いがあり、橋詰の整備などは特に意識的に取り組みました。