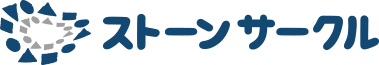特別企画
お墓や石について、さまざまな声をお届けします。
見事に蘇った常磐橋! ― ㈱文化財保存計画協会特任主任研究員 西村祐人さんに聞く
 完成した水切石
完成した水切石
■ 人間にとって、「技術とは何か」
中井 結局、人間にとって、「技術とは何か」ということだと思います。いまのものづくりの仕組みは現代日本の特有のものかもしれないけれども、現代文明のいろいろな制約や条件のなかでの合理性を持っているわけです。
ただ、文化財の場合、現代文明の文脈とはバッティングすることが多い。そのバッティングする部分の一つひとつをどう考えていくのか。矛盾を解消するのか、矛盾を受け入れるのかは、設計者の考えになってくると思いますが、いかがでしょうか?
西村 橋の表面は、元々はビシャンで叩いたあとに小叩きで仕上げられています。親柱であれば、砥石できれいに磨かれているのが当初の仕様です。ただいまは、最初の段階で平滑な面がつくれてしまいますので、それは大きな矛盾で、平坦な面を荒らしていくという行為は、フェイクではないのかと……。
中井 新しい石を補填するとか、昔の石を現代の技術で修復するといったことは、現場の石工さんとコミュニケーションをとり、指示をしていけばいいと思います。
しかし当たり前ですが、当時の石工さんは、いまはいませんよね。だから、当時の技術との対話というか、「なぜ、このようなものづくりがここでなされたのか」ということは、想像しなければならないと思いますが、昔の手加工の痕を見て、またいまのあり方を考えて、「このように組み合わせると面白い」といったことはありましたか?
西村 常磐橋の石積みは切り込み接ぎであり、大きな目地を取らずに石を積んでいくので、なめらかな曲線で不連続な部分があると、わずかな出っ張りがすぐに違和感につながってしまいます。だから当時の石工さんたちは、一石、一石をある程度加工し、仮据えし、最後は石を組みながらその場で加工していたはずです。
ただ今回、新補石を使う場合はまず型をとり、その型を元にして別の場所で石を加工し、その石を必要なところに入れました。その際、隣りの石との関係性や曲線が通っているかどうかはあまり確認せず、石工さんからは「型どおりに石をつくり指示通りに石を積んだ」といわれ、「でも、そうではないですよね」と対立するような場面がありました。
「そうではない」というのは、新補石が隣りあった石との関係のなかで、出っ張ったように見えるのであれば、型どおりにつくった石だとしても、「全体のなかでもう一度調整すべき」ということです。当時の人が石を積みながら調整していたという形跡は、随所で見ることができるわけです。
「製品をつくっている」という意識と、「組み上がる全体の一部をつくっている」という意識の違いが、いまの石工さんと当時の石工さんにあるのかもしれません。もちろん、いまの石工さんでも全体を見据えた上で個々の石をつくられている方もいらっしゃいますが、全体の傾向としては、「一石で完結した製品をつくっている」という石工さんが多いように感じます。
それは、石の角の納め方にもいえることです。現在は、多くの石屋さんが墓石をはじめ、製品を扱われていると思いますが、角が欠けた墓石は商品にならないと思います。
でも、常磐橋の現場では、「角は多少欠けてもいい。それが当時のあり方だから、細かいことはいいません」と伝えても、ピシッと角を出していただいたり、サンダーできれいな面をつくってくださったりして、現代の製品づくりになっていました。
 橋台の壁面。反り勾配で、また曲線であることから、加工も施工も難しい部分であった(写真提供:文計協)
橋台の壁面。反り勾配で、また曲線であることから、加工も施工も難しい部分であった(写真提供:文計協)
中井 文化財を扱っているといっても、石工さんは現代人です。現代人に「昔の技術でものをつくってくれ」「百数十年前と同じことをやってくれ」とはいえないですし、そもそも石橋を解体し、石を改めて積む際に、今回はジャッキアップをして計測して変位を万全にコントロールしながら、つまり現代の技術を駆使しながら積みましたよね。しかし当時は、当たり前ですがそのようなことはやっていません。
当時はある意味で、「歪んでもいい」くらいの精度で石を積み、あとは全体の見栄えがよく、構造的に問題がないように、「最低限の辻褄は合わせておこう」といった感じの、大らかなつくり方をされていたのだと思います。
それに対して、百数十年前に築造された常磐橋が文化財に指定されたといっても、今回の修復によって、「まったく別の橋というか、竣工当時よりも、はるかに立派になって蘇った」と私は思っています。
ですから、矛盾があったとしても、存在の仕方としてはあり得ると思います。
 ライトアップされた常磐橋(写真提供:文計協)
ライトアップされた常磐橋(写真提供:文計協)
■ 継承したいのは、文化財としての「かたち」ではなく、石との対話のなかで、つくり手の身体の延長線上に、ものが成り立っているという、その「あり方」
西村 いままったく新しい石橋を架けるのであれば、現代でなければできない技術を徹底的に駆使して、たとえばピシッと加工された本磨きの石だけを使い、鏡のような石橋をつくることなども数寄者の仕事としては面白いかもしれません。しかしそれが、石橋としての本質かというと、私は違うような気がします。
ですから今回は、「製品」ではなく、「構造」としての石の大らかな加工を取り戻したいと思っていました。でもそれは、石屋さんが普段求められているものではないかもしれません。ただその一方で、石屋さんも「それでよい」とは思っていないはずで、いまの製品づくりとは違う石との向き合い方を、どこかで求めているのではないかと私は密かに思っています。
石の加工に大らかさがないのは、昔ほど構造物として石を使わなくなったということに加え、時代とともに社会がピシッとした仕事を要求してきたからでしょう。石との対話のなかで生まれる何かが、完成したものに豊かな表情を与えると考えれば、石の角をしっかり整えることは、必ずしも大事なことではないと思います。
それはいつの時代においても変わらない、ものづくりの本質であるように感じます。「文化財だから」、「昔の技術だから」、「いまの技術だから」というのとは違う、もっと普遍的に大事な何かがあるのだと思います。
機械を使うということは、自分の手と石との間に、フィルターを一つ挟むことです。身体の延長として機械を使いこなせればいいのですが、逆に機械に使われてしまうと、でき上がるものはまったく違ったものになると思います。だから古い技術を蘇らせるとか、機械を使うからダメだということではなく、人間の傍らに技術があるかどうかが大事なことで、機械を使っても大らかなものはつくれるはずだと思っています。
一つずつの石に表情があり、それらの石が寄り集まって全体が構成されたときに、はじめて人に訴える力を持つことができると思っています。継承したいのは、文化財としての「かたち」ではなく、石との対話のなかで、つくり手の身体の延長線上に、ものが成り立っているという、その「あり方」なのかもしれません。
 敷石は神田橋の石材仮置き場で仮組みをした(写真提供:文計協)
敷石は神田橋の石材仮置き場で仮組みをした(写真提供:文計協)
中井 常磐橋とは少し話が外れますが、ダイヤモンド刃で石を切断していくものづくりには、人間性は残っていないのですか?
西村 私はあるとは思います。大口径にせよサンダーにせよ、手の延長線上にある道具と捉えるならばですが。ダイヤモンド刃を使って切断、加工するからこそできることが間違いなくあるし、その技術を駆使しないとできない仕事が存在します。現代の技術を使うからこそ出合える新しい石の表情はあると思います。
石橋や伝統的な構造物のつくりが、いまの技術体系とはまったく異なるなかで、無理にいまの技術を重ねてしまうところに不幸が生じるのだと思います。
中井 私の理解が正しいかわかりませんが、要するに西村さんは、「石橋は人間がつくるものなんだ」ということを叫びたいのですね。
西村 そうかもしれません(笑)。その復権がないと、血の通わない構造物になってしまう気がします。
中井 いまの構造物で「血が通っていない」と思うのは、どういった部分ですか?
西村 たとえば石を使って「〇〇風につくる」というときは、まったく血が通っていないと思います。
常磐橋で、不揃いの石をなぜそのまま残したかというと、「その石が文明開化期の世相を背負っている」という理念的な部分だけでなく、不揃いでも、大きい石は力のかかる下の方に使い、かたちが悪い石であればかたちのいい石で囲ってあげて真ん中に据えるなど、当時の人間の知恵や石への思いやりのようなものが残っているからです。その知恵の痕跡が消えてしまうことは、よくないことだと思っていました。
不揃いの石の集積でつくられた石橋のほうが、緻密に計算したものよりも構造的に、はるかに合理的なケースもあると思います。私たちが、その価値を評価する指標を持ち合わせていないだけであって、不揃いな石でも上手く積めば、それなりに強い石橋はつくれるはずです。
仮にいまの石工さんに常磐橋で使われた同じ石を渡して、「自由に石橋をつくってください」というと、見た目は同じでもまったく違った石橋になってしまうこともあり得ると思います。たとえば鉄骨組みであれば、いまの人が組んでも昔の人が組んでも、そう大きくは変わらないような気がします。それは、比較的均一な「部品」だからです。
材料に大きな違いがあります。石は自然のものであり、石目に合った使い方をしないと、上手く力を受けきれないとか、巣があるならば、そこに力が掛からないようにし、ヒビが入っていたら、その部分を避けて使うなど、一つひとつの石を適材適所で見立てないといけないわけです。
それは木も同じですし、大きな魚を解体し、その部位を適材適所に料理して使っていくことと同じかもしれません。いずれにしても、その見立てのなかに人間の手の痕跡が宿るような気がしています。