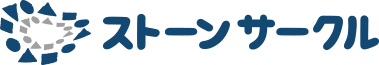特別企画
お墓や石について、さまざまな声をお届けします。
見事に蘇った常磐橋! ― ㈱文化財保存計画協会特任主任研究員 西村祐人さんに聞く
 現場内の休憩所(写真提供:文計協)
現場内の休憩所(写真提供:文計協)
■ 現場では、ケンカもたくさんさせてもらいました(笑)
中井 一番大きな壁は何でしたか?
西村 壁がありすぎて(笑)。最初の壁は、「洪水が発生すると、常磐橋が水の流れを阻害する可能性があるから、バラして修復するのであればどこかに移築できませんか」という話からスタートするわけです。治水安全性の立場に立てばそれもわかります。
しかし、史跡という価値に立脚し、ましてや土木構造物なので、地形や場所から切り離してしまうと、大事なものが失われます。その場所にあるのが一番ふさわしい。河川を管理する方々とはずいぶん時間をかけた対話が必要でした。それが一番大きな壁でしたね。
中井 常磐橋プロジェクトで、「こうすればよかった」「これは足りなかった」ということはありますか?
西村 できることはやりきったと思っています。
中井 では、100点満点?
西村 置かれた状況のなかでは、100点だと思っていますが、その状況を、「もう少し何とかできたのでは」という思いはもちろんあります。
中井 「全力投球した」という意味での100点ですね。修復が終わった常磐橋を客観的に見てどうですか?
西村 まだ修復が終わったばかりで、まだその延長線上にいます。正直、客観視できるほど時間が経っていません。いずれ振りかえらねばならないことだと思います。「ああすればよかった」「こうすればよかった」というのはないわけではないですが、時間や予算、関係性など現実のなかでは、やりきったという思いです。
中井 「やりきった」という思いはあっぱれだと思います。ただ、当然ながらプロジェクトなので、自分だけではなく、いろいろな人とチームで仕事をしたはずです。
現場でのチームワークのつくり方で、工夫したことや苦労したこと、思い出深いことなどはありますか?
西村 チームワークということでいえば、シンプルに現場に居続けたことだと思います。半常駐監理なので、原則、現場にはいるのですが、石工さんが石に触れている場面にできるだけ立会い、「何が上手くいかないのか」「何に悩んでおられるのか」など、作業や加工された石を見ていれば「手をどこで抜いたのか」も含め大体わかります。そういったコミュニケーションは常にやってきたつもりです。現場では、ケンカもたくさんさせてもらいました(笑)。
「設計者が意図するところは何なのか」が見えないなかでも、石工さんとしては、目の前の仕事にどんどん終いをつけていかねばならないわけです。いくら言葉を重ねても、まだ見えぬものを共有することは、本当に難しいことです。ときには、自分自身で道具を握ってやらせてもらうことで、理解していただけることもありました。
「この部分はこのような曲線でないと、常磐橋本来の優美さが伝わらない」といっても、「このような曲線」ではわからないわけです。その曲線を数値に変換して丁張りを張っていただくのですが、あくまでも点の連続です。点と点の間をどうつなぐかは、石工さんの力量次第です。何か違うというときには、石工さんと一緒にその間の曲線をテープで描き、仮に石を据えてみると、あるべき曲線がパッと見えてくるということもあるわけです。
私自身が、直接丁張りを設置したり、石工さんの道具を手にすることに、ためらいを感じる部分もありましたが、どうしても、ものを通じてでしか共有できなかったことはたくさんあったと思います。
 笠石の曲線の通りを確認する(写真提供:文計協)
笠石の曲線の通りを確認する(写真提供:文計協)
中井 そこまでして「共有してほしい」と思ったのは、どうしてですか?
西村 多くの人が常磐橋の解体・修復に時間やエネルギーとお金を投じているわけです。その結果、でき上がったものが、中途半端なものになってしまったら、誰も救われないというか……。
現場で仕事をしている皆さんは、「どのようなものができ上がるのかわからないけれども、設計者を信じてともかく頑張ろう」ということだと思います。しかし、その質や完成度を、少なからず設計者自身が見えているところまで到達させられなければ、皆さんの思いや苦労が社会から正しく評価をされないし、何よりも常磐橋の特質をできるだけ正確に未来へ継承したいと思っていました。
でもそれは、「私自身がこうあらしめたいだけなのではないか」という思いが一方ではあり、常にそのことをつきつけられていたように思います。
中井 現場の石工さんなどから学んだことはありましたか?
西村 最初のころは、教えていただくことばかりでした。石を角まで叩くと、どうしても欠けてしまうので、小叩きやビシャン仕上げで全周回したい場合、正面は大きめにつくっておいて、後からコヤスケで落とすという手順などですね。でもそれはいまの石の加工の仕方であり、昔は必ずしもそうではなかったということを後で知ることになるのですが。
常磐橋がつくられた当時の技術と、いまの技術は当然違うわけです。石を平滑にする場合、元来は矢で石を割り、ゴツゴツした面をノミでさらい、ビシャンでつぶして平らにし、最後に小叩きで仕上げ、場合によっては砥石で擦って平滑面をつくるという手順です。しかし、切削機械が導入されたいま、まったくその流れは逆になり、ダイヤモンド刃で切断した平滑な面を、ノミやビシャンで荒らしていくという作業手順になるわけです。
 水切石を積む(写真提供:文計協)
水切石を積む(写真提供:文計協)
伝統的な仕事を生業にしている一部の石工さんを除き、いまは、この手順が当たり前だと思います。そこで悩むわけです。たとえば現在、ノミ切り仕上げを施すということは石の平滑な面を荒らすということですので、一度仕上がった表面を、「風」に仕上げるということです。「風」である以上、何かそこには「嘘」があるのではないかという気分になります。
では、「新補石は切った面のままでいいのか」というと、それも違う。結局は、全体として残っている石たちとの調和やバランスのなかで、「どう調整するか」ということです。
逆に、石の背面など見えない部分は、現代の技術を尊重しました。昔の石には木や鉄の矢で割った矢穴の痕がありますが、新補石の場合は、ハンマードリルで穴を掘り、セリ矢で割った矢穴痕です。その痕が現代の技術で割った痕跡であるならば、それを「あってはならないもの」と考えて消すのではなく、「尊重して、そのまま残しましょう」とやってきました。
それは技術の本質にかかわることで、今日に至るまで、石を効率よく加工する技術はどんどん進化しており、その進化を否定したくないと、現場の石工さんとも議論しましたね。
 水切石の表面を仕上げる(写真提供:文計協)
水切石の表面を仕上げる(写真提供:文計協)
中井 昔ながらのやり方を導入したところもあったのですか?
西村 多くがそうでした。石の表面が小叩き仕上げであれば、ダイヤモンド刃で切断した面を小叩きで仕上げてもらいました。
中井 ただ、西村さんの考えでいうと、それはフェイクになるわけですよね。
西村 「フェイクになるのではないか」という気持ちを常に持ちながらやっていました。正直なところ、本当に何が正しいのか私のなかでも結論が出ていないものの一つであり、課題として残っています。