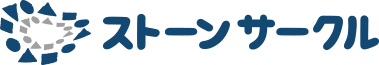特別企画
お墓や石について、さまざまな声をお届けします。
見事に蘇った常磐橋! ― ㈱文化財保存計画協会特任主任研究員 西村祐人さんに聞く
 現場に置かれた旧材と新補材(写真提供:文計協)
現場に置かれた旧材と新補材(写真提供:文計協)
■ 残念ながら技術は後退している
中井 いまの話で一つ気になったことは、専門家が不均質なものを見分けることができなくなってしまったら、技術の後退になると思います。これは大きな問題です。こういう、技術の本質が失われている事態に対して、私たちは何かしなければならないと思いますが、どう思いますか?
西村 残念ながら技術は後退していると思います。
石を適材適所に使うとか、石の面のどちらを表にしてどちらを裏にするかなど、本来意図的に選択されなければならない場面があります。直方体に切られた石が現場に入ってきたときに、小面が二つあれば、どちらの面も使えるわけですが、全体としてよりよいものをつくろうとすれば、二つのどちらかからよい面を選べる余地があるはずです。
それにもかかわらず、均質に切断された石は、どちらの面を使っても同じであるかのような錯覚を抱かせるのか、そのことが問われない場面によく出くわします。一人ひとり、一つひとつの作業工程において、選択する、見立てることを自覚すれば、よりよいものができるはずです。もちろん常磐橋では、そのような心掛けの石工さんばかりでしたが、石の世界全体としては、必ずしもそうだとはいえないのではないでしょうか。
中井 技術の後退は、石の世界だけではなく、現代のものづくりが全体として直面している危機であり、このことは20世紀の終わりごろからいわれてきました。この事態に対して、エンジニアとして今後、どう向き合っていきますか?
西村 石や木は自然物ですから、基本的なスタンスとして、「人間がすべてをコントロールできるものではない」というところに立たなければならないと思っています。いくらダイヤモンド刃できれいに切断しても、そもそも不均質な素材です。そのことにまず謙虚になることだと思います。
また、これまでは勘にだけ頼っていた部分が、解析の精度が上がることで捕捉できるようになったり、自然物の不均質さを再評価できる可能性もあります。「不揃いだから切り捨てる」ということがあってはならないと思います。
そこに現代のテクノロジーがサポートしてくれる余地があると思いますし、「技術を過去に閉ざさない」ということが大事だと思っています。テクノロジーのレベルが上がっていくことで、いままで切り捨てられてきた価値がものづくりのなかに制度や仕組みとして位置づけられる可能性もあるのではないでしょうか。そこはポジティブに信じていたいと思っています。
 日本橋クルーズで小型船に乗船すると、常磐橋を日本橋川から見ることができる
日本橋クルーズで小型船に乗船すると、常磐橋を日本橋川から見ることができる
中井 常磐橋修理工事専門委員会で、石橋が変形するシミュレーションを実際に出してくれましたが、それは20世紀にはできなかったことです。コンピュータの計算処理能力の発達はものすごいので、不均質性を科学的に捉えることはどんどん進んでいくと思います。
不均質なものが集まったときに生まれる価値をどう捉えるか。思えば、それこそ人間自身が不均質であり、現場に携わる人の性格も能力もバラバラです。その不均質な人間集団の価値を捉えたうえで、ものづくりに向けてコーディネートしていくことが私たちの仕事でもあると思います。
そういう意味で、今回の現場は100点満点ですか?
西村 そういうことからいえば、百点ではなく、課題はすごく多いと思います。仕事の仕方への共感が100%得られたわけではありませんし、思想レベルで、私が目指していることと、日々の生活のために仕事をするということの間にも大きなギャップは存在します。すれ違いも当然あります。
中井 そもそも人間が不揃いで不均質であるなかで、近代以降は、ある英雄的なアーキテクトのコンセプトとか、思想とか、方法論で、つまり個人の理性や精神で空間を統合制御するといったものが、どんどん価値を持つようになりました。それはものづくりの世界に限りませんが、人間をある意味、窮屈な箱のなかに押し込めてきたと思います。
昔のものづくりは、不均質な人間がワーと集まって、思うようにいかないことが多少あっても、その場で辻褄を合わせていたと思います。つまり、大らかさや遊びが許される世界。だから、よくよく見ると、いろいろとバラツキがあるのだけれども、トータルで見ると、すごく人間に対する肯定感のようなものが出てくるのだと思います。
私は吉村順三さん(建築家。1908-97年)をとても尊敬していますが、吉村さんがフランス中世のル・トロネ修道院を見に行ったときのことを、弟子の中村好文さんが回想録か何かで残していたと思います。その修道院は石づくりで、手仕事で完全に計算されているわけではなく、だから上手くいっていない部分もあって、それを吉村さんがニコニコしながら見ていた、といった文章でした。
西村 私のものづくりに影響を与えた本は二冊あり、一つはフェルナンド・プイヨンが著した『粗い石』(形文社)です。いま話が出たル・トロネ修道院をつくったときの工事監督の日記で、もう一冊は幸田露伴の『五重塔』(岩波文庫)です。
この二冊の根底にあるのは、いま先生がおっしゃったように、それぞれに手の痕跡があり、不揃いなものや人々の思いが集積統合され、ものができ上がっているということです。人々はそこに心を動かされるのであって、それは人間賛歌なのだと思います。
ただ近代は、その部分を奪ってきたのだと思います。人がものに関わることの手応え、そこに関わることによる生の実感、ものの成り立ちなどを、近代は切断してきたと思います。そのはく奪、切断されたものを取り戻すことが必要だと感じています。それは、何も昔に戻るということではありません。
一つひとつ、現場の人たちによるものづくりの集積が「もののあり方」であると捉え直せば、現在とはまったく違った建築家像が立ち現れてくると思います。逆に、そこから発想したものづくりを目指したいですね。
私は村野藤吾さん(建築家。1891-1984年)やフランク・ロイド・ライト(アメリカの建築家。1867-59年)の建築が好きで、二人とも近代の建築家ですが、ものづくりの本質を捉えた建築をつくられていたように思います。ものの成り立ちがわかり、手の痕跡が見えます。
中井 石や木、土でも何でもいいですが、近代になって失われたもう一つのことは、自然に対する謙虚な姿勢でしょうね。
西村 今回の修復でも、一度積み終わった部分を、無理をいって積み直してもらうことがありました。それは「石にきちんと向き合ってほしい」「近代以降の価値観に縛られる必要はない」という私なりのメッセージでした。
中井 西村さんの理屈に合わないから直してもらったのではなく、「石の理屈に合わないから」「自然に対して謙虚なものづくりのあり方に反しているから」ということですよね。
西村 そうですね。