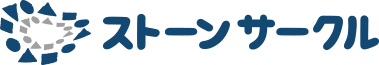特別企画
お墓や石について、さまざまな声をお届けします。
想像もしなかったものが、石に向き合っているときに生まれてくる―彫刻家 樂雅臣
 作品「輪廻 雷鳴」ポルトロ(大理石、写真:樂雅臣)
作品「輪廻 雷鳴」ポルトロ(大理石、写真:樂雅臣)
●インタビュー/「月刊石材」2020年2月号掲載
想像もしなかったものが、
石に向き合っているときに生まれてくる
彫刻家 樂 雅臣
*彫刻家 樂雅臣「石と空間の美」はこちら
樂焼の窯元に生まれ、石の彫刻家へ
――まず驚いたのは、450年続く樂焼の窯元・樂家のお生まれということです。幼少期からモノづくりがお好きでしたか?
樂雅臣氏(以下=樂) 好きでした。小さい頃から父(十五代吉左衛門・直入氏)に粘土を渡されていて、兄(十六代吉左衞門)と一緒に動物などをつくっていました。それはかなりの数になります。やはり物心がつく前の造形物というのはそのときにしかつくれないもので、いま見ても「どうしたらこういうものが思いついたのか」と、かなり不思議な面白さを感じています。
――表現は不適切かも知れませんが、とても特殊な環境と思えます。そこから刺激や影響を受けているといえますか?
樂 それは気付かぬうちに刺激を受けているから、彫刻家という仕事を選んだのだと思います。実家にいるうちはそれが日常生活でしたが、大学(東京造形大学)で東京に出てから「ウチはいい環境なんだ」と気付かされました。京都にずっと住んでいる方が東京に行ったときに、改めて京都の良さがわかったり、もっと知りたいと思ったりすることと似ています。
物を見ることに関しては、小さい頃からお茶碗などいろいろなものに触れられる環境にあり、また父の友人や知り合いの方とも一緒に過ごさせていただきましたので、そういうことも含め、本当にいい環境で育ったと思います。
そのせいか、つくることが本当に好きで、幼いながらに粘土をこねていましたが、いざつくることを将来の仕事にしようと思い、粘土以外の素材を考えても、そのときにはまだ答えがみつかりませんでした。
――ご長男が樂家を継いだら、樂さん自身が陶芸の道に進むということはないのですか?
樂 樂家は一子相伝。たとえばお茶碗を窯で焼くときなどは、僕も含め大勢で手伝っていますが、お茶碗をつくるのは、樂家でいえば〈吉左衞門〉を継ぐ者にしか許されません。
そして本来、家を継がない男子が結婚して家を出るときには養子に入り、姓を変えないといけませんでした。ただ僕は両親の思いにより、結婚後も樂の姓のままです。
――やはり厳格なのですね。陶芸以外の〈つくる仕事〉をしたいと思ったのはいつ頃ですか?
樂 中学生のときです。小学校時代はもうがむしゃらに遊んでいて(笑)、ただ中学校に入ると少し精神年齢も上がり、学校生活が合わなくなって、いわゆる登校拒否になりました。
といっても、誰かに迷惑をかけたり、ずっと部屋に引きこもっているわけではなく、いまアトリエがある近くの山林などにぶらぶら行ったりしていて、そういうなかで「表現の道に進みたいな」と考えました。学校に行っていない分、自分のことを考える時間がかなりありましたからね(笑)。
ただ、そのときにもまだ〈石〉という選択肢はありませんでしたね。
――彫刻家になろうと思ったのはなぜですか?
樂 生まれた家が樂家だったことも影響していると思います。そして実は祖父・覚入(十四代吉左衞門、1918‐1980年)も、父も東京藝大の彫刻科(東京藝術大学美術学部彫刻科)を出ていまして、そういう流れもあって、僕も彫刻家を目指しました。
――十四代目も十五代目も石に触れているんですね。お二人は樂家を継がれたのに、なぜ彫刻を学んだのでしょう?
樂 二人とも石の基礎は学んでいます。
陶芸でも、樂家では「手捏(てづくね)」といいまして、手でカタチをつくっていきます。一般的な陶芸は轆轤(ろくろ)でまわしながら粘土を引き伸ばしたり、削り出しますが、樂家では轆轤を使わず、試行錯誤しながら、自分の手のひらのなかでカタチを追求していきます。そういうものの見方、つくり方というのは彫刻に通じるのです。
 京都での大規模な個展「彫刻家 樂雅臣展」の会場風景。黒い石(ジンバブエブラック)による作品「輪廻」シリーズを薄暗い空間のなかに複数展示し、黒い石の存在感、力強さ、美しさを引き立てた(2017年、美術館えきKYOTOにて、写真:樂雅臣)
京都での大規模な個展「彫刻家 樂雅臣展」の会場風景。黒い石(ジンバブエブラック)による作品「輪廻」シリーズを薄暗い空間のなかに複数展示し、黒い石の存在感、力強さ、美しさを引き立てた(2017年、美術館えきKYOTOにて、写真:樂雅臣)
 上と同じ個展「彫刻家 樂雅臣展」の会場風景だが、こちらは一転、白い空間のなかに作品「Stone box」シリーズを複数展示し、展覧会の会場の雰囲気をがらりと変えた。石は透過性があり、作品の内部を予感させるオニックスを使用している(2017年、美術館えきKYOTOにて、写真:樂雅臣)
上と同じ個展「彫刻家 樂雅臣展」の会場風景だが、こちらは一転、白い空間のなかに作品「Stone box」シリーズを複数展示し、展覧会の会場の雰囲気をがらりと変えた。石は透過性があり、作品の内部を予感させるオニックスを使用している(2017年、美術館えきKYOTOにて、写真:樂雅臣)