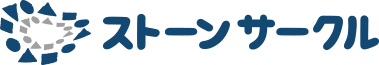特別企画
お墓や石について、さまざまな声をお届けします。
日本人はなぜ、お墓を石でつくってきたのか―石造物研究家 大石一久
 長崎・日島の中世古墓群(長崎県新上五島町)。中央(畿内)の影響が見られる五輪塔や宝篋印塔が建てられ、「日引石」(福井県、安山岩質凝灰岩)の石塔も多い。同じ長崎・対馬の青海と同じく、礫丘状の海岸に築かれた海岸墓地で、同様に海の彼方を意識した死生観を感じさせる
長崎・日島の中世古墓群(長崎県新上五島町)。中央(畿内)の影響が見られる五輪塔や宝篋印塔が建てられ、「日引石」(福井県、安山岩質凝灰岩)の石塔も多い。同じ長崎・対馬の青海と同じく、礫丘状の海岸に築かれた海岸墓地で、同様に海の彼方を意識した死生観を感じさせる
●インタビュー/「月刊石材」2022年1月号掲載
日本人はなぜ、
お墓を石でつくってきたのか
石造物研究家 大石一久
全国的にお墓(墓石)離れが危惧されるなか、私たちはお墓による供養(建墓・墓参)の本質的な意味合いを、社会へ伝え続けなくてはいけません。では、そもそも日本人はなぜ、お墓を石でつくってきたのでしょうか。そのヒントを得るために、濃密な石文化が根づく長崎県を地盤に広く中世石塔などの石造物を調査・研究する大石一久先生に、その研究成果を踏まえて普遍的な日本人の死生観、そのなかでの石の存在意義などを探っていただき、日本人が石のお墓にこだわってきた理由や背景を考察いただきます。
はじめに
ふだん私たちが何気なく見過ごしている石塔は、私にとっては宝物がいっぱい詰まった玉手箱です。いつ頃、どこで、どんな人々が建てたのだろうか、なんでお墓は固い石でつくられる必要があったのだろうか……次々に出てくる疑問を紐解(ひもと)いていくと、それまで想像だにできなかったすごい世界が見えてくるのです。
私はお墓や石塔類(主に墓石)を資料として歴史を探っています。講演会などでも、「どうして石塔の研究を?」とたびたび聞かれます。「名前が大石だからですよ」と冗談で答えるのですが、私が生まれたのは長崎県平戸島(平戸市)で、幼少期によく祖父に連れられてお墓などの古い石造物を見に行きました。祖父は研究者でもないのに詳しくて、「これはいつ頃つくられたものだよ」などと説明してくれるのが、子供心に楽しかったんですね。そうした実体験が、いまの私の研究のベースになっていると思います。
今回は「日本人はなぜ、お墓を石でつくってきたのか」をテーマに、私の研究成果の一端をお話しいたします。
石の霊力――生きている石
私の故郷・平戸島には「生きている石」がいくつもあり、古来より島の人々の信仰の対象として大切にされています。つまりそれは“成長する石”のことで、たとえば「トビニュー石の神」(平戸市高越町、鎮守神社)が挙げられます。それはこんな話です。
――ある小石がシラス漁の地引網にかかって網を破る。沖に運んで捨てても、また戻ってくる。これが何度か続くので、困った村人がその小石を神社の境内に飾り石として置くと、さらに困ったことに日ごとにその小石がどんどん大きくなってくる。このままでは天まで伸びてしまうから、石のてっぺんの芽(め)を切り、“ニュー”と呼ばれる茅(かや)を着せて輪で締め、その成長を止めている――
「トビニュー石の神」では、いまも毎年10月9日のお祭りのときに新しいニューに着せ替えています。
 「トビニュー石の神」(長崎県平戸市、鎮守神社)
「トビニュー石の神」(長崎県平戸市、鎮守神社)
生命を持ち、成長する石にニュー(茅)をかぶせてお祀りし、いまも毎年10月に新しいニューを着せ替える
また、こんな石の話もあります。
――あるときに三吉という農夫が鋤(すく)の神という山中から、牛の片荷の重石として持ち帰った石を家の庭先に置いておくと、いつの間にか戸口まで戻ってきている。不思議なことに、牛の病気や怪我に霊験を現すので、牛神様として祀るようになると、今度は大きく成長し、小石を産むようになった――
その石はいまも平戸市生月町の保食(うけもち)神社の祭神・保食神(うけもちのかみ)として祀られています。
 石(保食神)を映す保食神社のお札
石(保食神)を映す保食神社のお札
実はこのような「生きている石」は、平戸島に限らず全国各地にあるもので、その代表的なものが国歌『君が代』に詠(うた)われる「さざれ石のいわほとなりて」です。この歌は10世紀に編纂(へんさん)された『古今和歌集』に収められた短歌がもとになっていますが、「さざれ石(小石)がだんだんと大きくなって巌(いわお)になるまで、君の世が続きますように」という祝いの歌です。
このように、日本人にとって石は、古来より“生きているモノ”であったのです。自然界のあらゆる物事に生命(いのち)を見出していたかつての日本人は石にも生命を見出し、石を生命ある有機物として捉え、さらには霊石(れいせき)や磐座(いわくら)信仰に現れるように、石にさまざまな霊や神が宿ると考えました。それは、神道や仏教が成立する前から私たち日本人が持っていた感覚、感性です。そしてこれこそ、日本人が石にこだわってきた大きな理由の一つであると、私は考えます。
石は単なる無機物ではありません。私たちと同じく生命を持ち、呼吸をしているのです。そして依(よ)り代(しろ)となって神や霊を宿し、またそれ自体が強烈なエネルギーを持つ霊石として成長し、子を産む。「中臣大祓詞(なかとみのおおはらえのことば)」(神道の祭事に用いられる祝詞〈のりと〉の一つ)によれば、もともと岩も木も草も人間と同じように言葉をしゃべっていたといいます。しかも石は、水、土、植物、動物、人間と続くすべての存在の一番根っこにあり、そこが祝詞でいう「磐根(いわね=地の底にある岩、地の底)」につながるのだそうです(須田郡司『日本の聖なる石を訪ねて』祥伝社)。であるなら、『君が代』に石が成長するさまが詠われているのも納得されますし、その背後にある日本人の石に対する深い思想がよく理解できます。
私たち日本人が石にこだわって石塔や石仏をつくったのは、堅固な石に永遠性を見出したことはもちろん、石そのものの持つ不思議な霊力に深い思い入れがあったからに違いありません。かつての日本人は、豊かな感性、ひいては視覚を超えた豊かな想像力のなかにありました。そこでは、石は人為(じんい)を超えた精神性やパワーを備えたスピリチュアルな霊石となります。だからこそ、何かに日々の暮らしや死後の安寧(あんねい)を託そうとしたとき、石こそが願いを叶(かな)えてくれる最適の素材と考えたように思われます。
この他にも、日本人が石にこだわってきた理由があります。それは「死後、海の彼方(かなた)や山の彼方で祖霊になる」という死生観に深く関係しています。海であれ、山であれ、「彼方」でつながっているわけですが、ここでその理由がわかる一つの事例を紹介しましょう。
国境の島・長崎県対馬(つしま)の西海岸にある青海(おうみ)という集落での事例です。