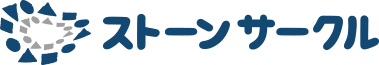特別企画
お墓や石について、さまざまな声をお届けします。
日本人はなぜ、お墓を石でつくってきたのか―石造物研究家 大石一久
対馬・青海に見る日本人の死生観
「あの世」と「この世」をつなぐ石
長崎県内をはじめ全国各地の海に面した集落では、大概、石ころだらけの海岸や砂浜などに墓地が築かれています。このような海岸墓地は、海際(うみぎわ)ぎりぎりの場合もありますが、その多くは波浪(はろう)で揺り上げられ、やや高くなった場所に築かれているのが一般的です。といはいえ、大型の台風など、数年単位で襲ってくる大時化(おおしけ)のときなどには、地上の墓石はいうに及ばず、埋葬された遺骨までもが深くえぐり取られ、高波にさらわれることがあったと思います。
だから、墓地をできるだけ子孫に伝え残そうとするならば、わざわざ海岸のそばに築くのではなく、災害の恐れが少ない山手の高台に築くはずです。それなのに、なぜ被害が予想される海際に墓地を築いたのでしょうか。
いまの私たちには不思議としか思えませんが、実はそこにはかつての日本人が持った深遠な死生観があったのです。ここでは、実際に私が調査した対馬の青海に残る海岸墓地から、その死生観に迫っていきたいと思います。
対馬における海岸墓地とその死生観に言及した著書に、大江正康の労作『対馬の海岸墓地から神々誕生』(対馬国界クラブ)があります。これによりますと、対馬の各浦々に築かれている海岸墓地では、台風などの災害で墓石や遺骨などがさらわれて海中に流されても、それは自然界の営(いとな)みとして何ら問題視されていません。むしろ遺骨などが海中にさらわれることで、「故人は海の彼方で祖霊に昇華(しょうか)する」という考えがあったそうです。よくいわれる「常世(とこよ)の国」(古代日本で信仰された海の彼方にあるとされる異世界)や、沖縄の「ニライカナイ」(他界概念)、折口信夫(おりくちしのぶ、民俗学者、1887-1953年)の「まれびと」(外部=他界からの来訪者、折口によって提示された概念)などに通じる死生観といえます。
青海(対馬市峰町)は対馬の西海岸に面した集落で、両側を急斜面の尾根が囲み、その間の海側を底辺にした二等辺三角形状の扇状地に広がる小さな村落です。現在の戸数は20戸ほど。両側の山裾(やますそ)にそって集落が形成され、その背後の山腹には段々畑が開かれて、かつては「木庭(こば)づくり」(焼き畑)で麦や蕎麦などが耕作されました。目の前の海は荒く、礫丘(れききゅう)状となっているために港を築くことができず、海藻を保存するための石積壁の藻小屋(もごや)も荒々しい海に背を向けてつくられています。
礫丘状の海岸部は地元では「エジリ(江尻)」と呼ばれていますが、墓地は、その荒波迫る海岸ぎりぎりのエジリに築かれています。後代(対馬・青海では17世紀半ばから)に民衆に関わる寺院ができて両墓制(供養する石塔は寺院境内に建立)が始まると、エジリは死体を埋めるだけの埋め墓としてありました。
 青海の海岸墓地の遠景。写真中央が墓地(下の写真が近景)。現在は防波堤で護られているが、古くは埋葬した遺骨(遺体)が大波にさらわれ、海の彼方で祖霊となり、石を依り代として里に戻るという信仰があった
青海の海岸墓地の遠景。写真中央が墓地(下の写真が近景)。現在は防波堤で護られているが、古くは埋葬した遺骨(遺体)が大波にさらわれ、海の彼方で祖霊となり、石を依り代として里に戻るという信仰があった
 長崎・青海(対馬市峰町)の海岸(エジリ)につくられている現在の海岸墓地の近景
長崎・青海(対馬市峰町)の海岸(エジリ)につくられている現在の海岸墓地の近景
『楽郊紀聞』(らくこうきぶん、幕末の対馬藩士・中川延良がまとめた随筆集)によれば、嘉永六年(1853)の記録として、青海では「人死すれば海べたの石原に葬る」「小石のおびただしく有所にて、土は少しもなし。其(その)小石をかきのけ、穴を穿(うが)ちて葬るなり」。また、新たに墓穴を掘った際、「古骨に逢ひても、穢(けがら)はしとも、悲しとも思はず。昔よりかくの如くなれば、誰が墓という事も曾(かつ)て知れず」「さて葬りし後は、其家の者も又顧(かえりみ)る事もせず。実に野に捨てしよりは、埋(う)め置(おく)だけがましなれ共、実は捨たる也」と書かれています。
つまり、「人が亡くなると、海ぎわの石礫(せきれき、小石)だらけのところを掘って葬り、その際にたとえ古い骨が出てきても誰の骨ともわからないし、汚(けが)らわしいとか悲しいなどという感情は起こらない。葬ったあとも家族などがお詣りに行くこともないし、野に捨てるよりは穴を掘って葬るだけまだましなほうなのだが、実際には捨てたも同然」と書かれています。
さらに「波打ち際より、石垣なども築たる内なれば、常に潮水は来らず。大波の時などは、洗ひ流しもすべし」とあり、意訳すると「海際とはいえ、石垣などを築いて少し高くなった場所に葬るので常日頃は潮水は入ってこない。しかし大時化のときなどは浸水があって洗い流される」とも記述しているのです。
このように、エジリの墓はまさに捨て墓そのもののように思われます。ごく普通にモノを捨てるように海岸の小石をかきのけて墓穴を掘り、死者を葬り、そこには悲しみや汚らわしいなどの感情も起こらず、だから埋葬後も、残された家族や近親者がその地に出向いてお詣りすることもなく、数年経てばどの場所に誰を葬ったかさえも忘れ去ってしまう――。
ところが、このエジリでの一見、冷酷とも思える葬送には実に深遠な死生観が存在していたのです。それが寄神(よりがみ)神社という、エジリから約200メートル南に下った海岸のそばにある神社との関係です。その寄神神社は、里で祭り事があるたびに、祖霊が海の彼方から満ち潮に乗って漂着する場所といわれています(寄神=「海の彼方から来る神」の意)。しかも寄神神社のご神体は白い布に包まれた2個の海石で、いまも祭り事があるたびに、その白い布は丁重に取り換えられるといいます。
この海石は何なのでしょうか? 『津島記事』(東京堂出版)に次のような伝承があります。
「応安年間(14世紀後半)に青見国広という人物が『翌未明、神である余(よ)が海辺に来るので祭るべし』という夢を見た。そこで翌朝、海岸のほうを見ると、確かに黄石が2個、波に乗って岸辺に漂着した」

 青海の海岸墓地のすぐ隣りの入り江に建てられている寄神神社。海の彼方で祖霊になった先祖が、祭り事のたびに満ち潮に乗って漂着する場所。ご神体は2つの海石で、祖霊が憑依する石ともいわれている
青海の海岸墓地のすぐ隣りの入り江に建てられている寄神神社。海の彼方で祖霊になった先祖が、祭り事のたびに満ち潮に乗って漂着する場所。ご神体は2つの海石で、祖霊が憑依する石ともいわれている
また、集落に残る他の伝承では、「阿比留家の先祖が舟で漁をしているときに海に浮く石を発見し、その石を祀ったのが始まり」ともいわれています。でも、いずれにせよ、寄神神社のご神体である2個の海石は、神となった先祖の霊(祖霊)が海の彼方から帰ってくるときに憑依(ひょうい)した石であったようです。
つまり、青海のエジリに埋葬された死者の魂は大時化の際に海中に入り、海の彼方で祖霊となり、里で祭り事があるたびに満ち潮に乗って寄神という場所(神社)に里帰りする。そして、その先祖の霊は2個の海石に憑依してこの世に姿を現す。石を介して、死後の「あの世」と現実の「この世」とがつながっているのです。
この寄神神社に見られる祖霊との関係は、対馬の他の場所でも確認されます。
たとえば、上県町(かみあがたまち)御園(みその)の森乃神社では、江戸時代に「寄神 祭里人之祖霊神体石」(『津島記事』)とあり、寄神は里の人々の祖霊であり、石をご神体として祭っています。また豊玉町の明嶽神社でも、「古先祖祭之神也」(『対馬州神社大帳』)とあり、寄神が祖霊神と深く関わっていたことが理解されます。さらに厳原町(いづはらまち)阿連(あれ)集落の場合は、祖霊が里帰りする寄神の場所と祭りを行なう氏神が離れているため、氏神のところへ続く山の尾根に「潮かき道」という祖霊だけの専用道路があり、祖霊はそこを通ってお祭りをする氏神まで向かいます。その際、祖霊は海岸の玉石や御幣(ごへい)に憑依して、目に見えるもの、触ることができるものとして各家に迎えられたといわれています。