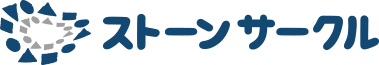特別企画
お墓や石について、さまざまな声をお届けします。
日本人はなぜ、お墓を石でつくってきたのか―石造物研究家 大石一久
対馬・青海に見る日本人の死生観
石は先祖の霊(祖霊)の実態
このように対馬の各浦々では、人々は亡くなると海の彼方で祖霊となり、里で何かの祭り事があると、満ち潮に乗って里帰りするのです。だから、先述の青海のエジリでの埋葬はそれを意識した行為であり、波浪によって遺骨などが海中にさらわれるのは災害ではなく、死者の霊を海の彼方に送り出し、祖霊に昇華させるための重要なプロセスだったことがわかります。
青海の人々にとって死者を埋葬し、その魂を海の彼方に送ること(葬式)が、いかに大切な儀式だったかがわかります。『楽郊紀聞』の記述だけを見ると、現代人には冷酷な葬送に思われがちですが、その死生観は祖霊信仰に基づくとても深遠なものだったのです。
哲学者・梅原猛は『日本人の「あの世」観』(中央公論社)のなかで、「アイヌや沖縄において、葬式が最も大切な宗教儀式であるかがよく理解されます。魂をあの世へ丁重に送るのは、再び魂をこの世へ送り返さんがためであります。魂がこの世に無事帰ってくるためには、まず、あの世へそれを無事送らねばならないのであります」と述べています。
まさに、青海での葬送がそうです。魂がこの世に無事帰ってくるためには確実に魂をあの世に送らねばならない。だから、条件の悪い石ころだらけの海岸に墓穴を穿ってまで、死者の魂を確実に海の彼方のあの世に送ったのです。そして波浪により海の彼方まで運ばれた死者の霊は、そこで尊い祖霊になる。その祖霊は一方通行的に彼方に留まるのではなく、里で祭り事があると満ち潮に乗って帰り、最初に寄神という場所に集まるのです。
さらに注目すべきことに、寄神神社のご神体が2個の海石であるように、祖霊は石(真砂=まさご=石など)に憑依して神社まで行き、また各家庭へと帰って行くと考えられていました。そして祭り事が終わると、祖霊は引き潮に乗って彼方へと戻る。これが仏教に取り入れられて精霊流しになったわけですが、重要なのは祖霊が真砂石に憑依しているということです。だからその石を海岸に積み上げたり、家へ持ち帰ることもあり、またお墓にも持って行って供えています。
 祖霊の依り代である丸石(真砂石)はお墓などにお供えする。左2点は長崎県平戸市の根獅子墓地(下の写真が墓地の遠景)。右は神社に関わる大岩に供えられた真砂石(平戸市堤町)
祖霊の依り代である丸石(真砂石)はお墓などにお供えする。左2点は長崎県平戸市の根獅子墓地(下の写真が墓地の遠景)。右は神社に関わる大岩に供えられた真砂石(平戸市堤町)
これは青海や対馬に限らず、海に囲まれた日本列島各地の海岸墓地でも、同様の習俗・信仰があったと、私は考えます。また山地では“山の彼方”になり、その場合、祖霊は樹木や草花に憑依するなど、少しロマンチックになりますが、でもどこに降りてくるかというと、磐座に代表されるような石なのです。
古来より、日本人にとって石は、先祖の霊やいろいろなものの霊、また神が憑依するものでした。特に死者との関係性から見ると、石はあの世とこの世をつなぐ接点であり、同時に石そのものに“祖霊の実態”を見出していたのではないかと、私は考えます。それが日本人の伝統的な死生観の一つであると思います。
繰り返しになりますが、日本人にとって石は人為を超えたスピリチュアルな存在であり、なおかつ、祖霊の実態でもあった。そしてそこに石の持つ永遠性を重ね合わせて、お墓を石でつくることで“死後の安寧(往生)”を石に託し、また、後で述べますが、末法(まっぽう)の世に故人を救うための“唯一の証(あかし)”としたのです。だからこそ、私たち日本人は古来より石にこだわって死者を弔(とむら)ってきたのだと思います。
整理しますと、石にこだわってきた理由は、①人為を超えたスピリチュアルな存在、②祖霊の実態、③永遠性ということになります。
 海岸沿いに築かれている平戸市の根獅子墓地
海岸沿いに築かれている平戸市の根獅子墓地
葬式仏教と石塔の広まり
古代の日本において、古墳などの有力豪族の墳墓は別ですが、もともと死体は河原などに棄(す)てられるもので、懇(ねんご)ろに葬(ほうむ)るなどという習わしはありませんでした。9世紀頃になると天皇の墓(陵墓)でさえもその所在が忘れられてしまうほどですから、庶民の墓に石塔を建てるなどということはなく、強いていえば、松や榎(えのき)などを土葬の墓に植えて墓標(墓標植樹)としたぐらいです。いまでも二本松・三本松など、「松」のつく地名がありますが、これらは墓地に関係した場所に多く使われています。
石塔は12世紀頃から出てきますが、墓地に墓石として建てられ始めるのは主に13世紀頃からです。それまでは仏教者といえども“死の穢れ”を恐れて、葬式にはあまり積極的ではありませんでした。ただ、13世紀に日蓮宗や浄土真宗、曹洞宗などの鎌倉新仏教が成立すると、それまでのタブーを破り、慈悲(じひ)の願いから仏教による葬式を本格的に執(と)り行なうようになります。いまでいう「葬式仏教」の始まりです。
現代社会では、ときどき寺院を「葬式仏教」などと揶揄(やゆ)する言葉を耳にします。確かにいまは葬式や法事などのときぐらいしか僧侶に接する機会がなく、人々の救済願望に応える姿勢を実感できずに、いわば仏教の堕落した姿として「葬式仏教」という言葉が使われます。
ところが、僧侶が葬式に関わるようになったのは、まさに革新的な出来事だったのです(松尾剛次『葬式仏教の誕生―中世の仏教改革』平凡社)。本来、僧侶は葬式に関わることはなく、むしろそれは忌避(きひ)の対象でした。お釈迦さんだって自分の葬儀に弟子たちが関わることを戒(いまし)め、修行に励むよう諭(さと)しています。
 松の木の枝を墓標として植樹した例(佐賀県嬉野市)
松の木の枝を墓標として植樹した例(佐賀県嬉野市)
では、何故に僧侶は葬儀に関わらなかったのでしょうか。そこには仏教などの影響で出来上がった独自の考え方がありました(高取正男『神道の成立』平凡社)。いわゆる“穢れの思想”です。死や出産、肉食、月事、火事などに接したら穢れがつくという考えで、なかでも一番重い穢れが人の死や埋葬でした(『延喜式』、平安時代中期に編纂された法令集)。当時、官僚的立場にあった僧侶(官僧)は天皇や神々の前でお経をあげるため、常に清浄であることが求められました。そこで僧侶は、穢れが一番重い葬儀を極力避けたのです。
ところが鎌倉時代になり、日蓮宗や浄土真宗、曹洞宗など新たな仏教が成立すると、僧侶も役人的な立場ではなく、私僧(遁世僧=とんせいそう)として自由な立場になり、死の穢れをもろともせずに葬儀に従事するようになります。ここに葬式仏教は成立し、江戸時代になってお寺と檀家の関係が義務化(キリシタン禁制のための寺請制度や檀家制度)されたことで、現在に至る葬式仏教が確立したといえます。
平安時代の終わりから鎌倉時代初めにかけて制作されたと考えられる『餓鬼(がき)草紙(ぞうし)』に描かれているように、それまで庶民が亡くなると、死体をそのまま遺棄する、いわば風葬が一般的でした。しかし新仏教の成立により、僧侶が民衆に寄り添い、死者を荘厳な儀式・儀礼であの世へ送るようになります。それが本来の「葬式仏教」という意味なのです。
そして、この葬式仏教の普及により、石塔の造立も進んでいくことになります。とはいっても、これは後述しますが、当初から石塔を建立できたのは主に有力官僚や高僧などの上位クラスの人々で、それが庶民にまで広まるのは江戸時代の寺請制度以降になります。
一方で新仏教が成立する前の平安時代にも、それまで穢れを忌避してきた官僧のなかから往生を願う結社を結ぶ者が現れました。それが比叡山延暦寺の官僧・源信(げんしん、942―1017年)らで、「二十五三昧会(ざんまいえ)」と呼ばれる葬送共同体を結成し、「世俗のタブーを憚(はばか)ることなく葬送を行なう」とまで宣言しています。それが契機となり、その後は武士や有力者などの間でも念仏講、六道講などが結成され、五輪塔などの石塔が造立されるようになります。
ちなみに、五輪塔はもともと死者を守るべく、大日如来が坐禅をする姿を表した石塔として、平安時代に日本で成立した石塔です。